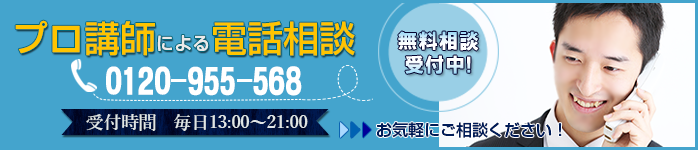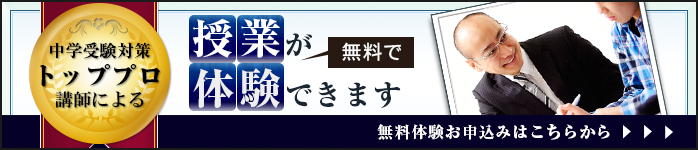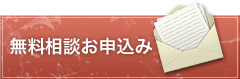突撃・取材ルポ
開成中入試対策・【2】6年間の学習カリキュラムをここで確実に理解しておこう!!(4ページ目)
② <社会>
開成中学では、6年間一貫教育の利点をいかして、単なる知識の詰め込みや暗記に終わらない、しかし、一定の質を持った授業を心掛けています。生徒に意見を尋ねる授業、調査・発表形式の授業、地図や統計資料を使った手作業、視聴覚機材の利用など多様な展開をしています。また、修学旅行で訪れる京都・奈良や開成の周辺をフィールドとして調査、発表を行う地域学習は、歴史・地理と深く関連させて実施しています。
開成高校では、高校の社会科は地歴科(世界史・日本史・地理)と公民科(倫理・政経)の5科目(そのうち、高1世界史・政経と高2倫理は必修)を学習しますので、進め方は少し複雑になります。限られた時間のなかで分化しつつ、それぞれ関連を持つ社会科各科目をできるだけ広く学べるように工夫をしています。
たとえば日本史では高校1年時に近現代史を中心に学習し、高校2年からあらためで時系列にそった学習をします。政経や倫理では、単なる知識の確認に終わらないように、議論をしたり、文章をまとめ発表したりするなどの時間を設けています。高校3年まで選択した科目を継続して学習することで、その科目について、広く深い知識が得られるように学習内容を配置しています。
③ <数学>
内進生は中学からの6ヵ年、緇入生は高校からの3ヵ年を見通したカリキュラムの大きな枠組みがあり、その中で、教材や授業展開の方法など細かな工夫日々重ねながら、教育を実践しています。
開成中学では、三つの学年とも、式・計算を中心とする授業と。図形を中心とする授業が並行して行われています。(名称:数学A、数学B)
<式・計算を中心とする授業>
計算や方程式の解法、関数のグラフの扱い方などについて。日々演習を重ねていくことによってしだいに熟達し、いろいろな代数的な技術が自然に身に付くように工夫して授業を行っています。
<図形を中心とする授業>
個々の図形がもつ細かな性質の理解を目指す一方で、個々の図形を統括している根源を探っていきます。紀元前からの天才たちによって築かれてきた数学の流れを踏まえ、たった数個の公理によって図形という世界が構築されていく様子や、その際に重要になる数学の厳密な論理も紹介していきます。
しだいに、高校の内容に踏み込んでいきます。中3では主に高校の内容を扱い、2種類の授業の内容も互いに影響し、融合されていきます。
開成高校では、各学年とも、二つの異なる授業(名称:数学αと数学β)が並行して行われています。
(高1)
中学から進学した内進生は、中学で学んできた内容に継続して、じっくりと高校の範囲の数学に取り組んでいます。
高校から入学した編入生は、高校の内容を一から始めますが、高1の終わりには、内進生と進度が一致するように、授業を展開していきます。授業時間は開成中学から進学した場合よりも週1時間多く、補講も実施しています。
(高2)
数学aは、全員共通の内容で、1学期は講義、2学期からは開題演習を行っています。数学βは、1学期は全員共通で微分を学びますが、2学期からは、二つのコースに分かれます。積分の講義を受けるコース(王に理系)、問題演習などのコース(文系)です。
理系を志望する生徒が大学受験に必要な範囲も、高2終了時には修得済みになり、標準的な問題の解法も身に付くようにカリキュラムを工夫しています。
(高3)
全員共通で、問題演習中心の、高度な入試の内容に対応した実践的な授業を行っています。さらにそれとは別に、理系用の問題演習を中心とした授業も展開されています。
開成中入試対策・関連記事一覧
開成中入試対策・突撃・取材ルポの記事
他校の突撃・取材ルポの記事
記事はいまのところありません。